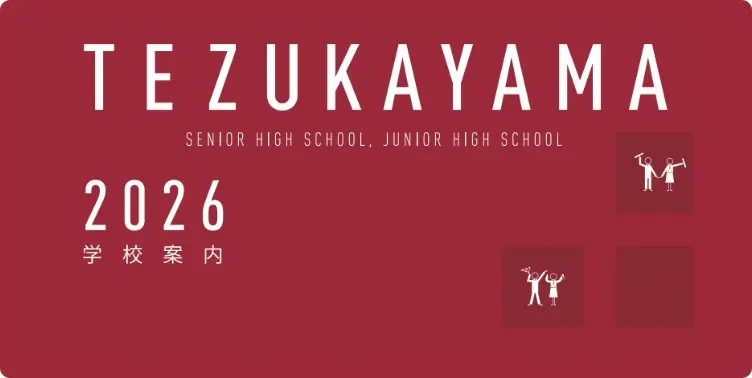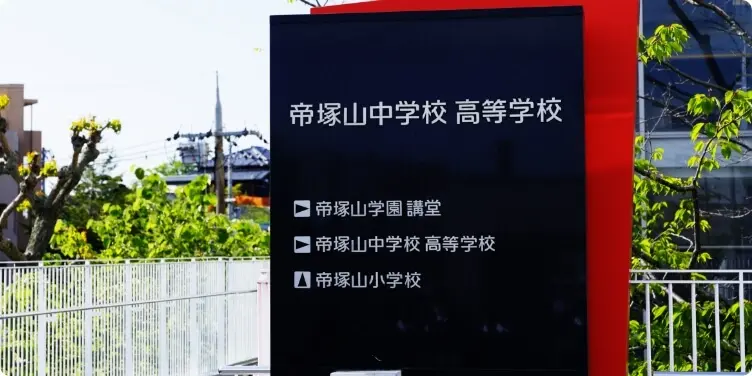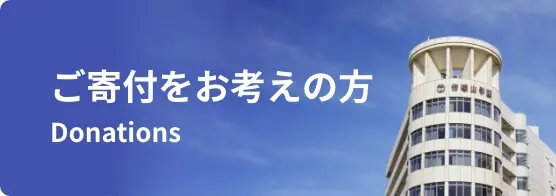歴史
帝塚山学園は、昭和16年2月28日に設立され、同年4月には奈良市学園南(当時・奈良県生駒郡伏見村)に旧制帝塚山中学校を開設し、その歩みを始めました。当初は7年制旧制高等学校の設置を構想していましたが、制度上の制約により中学校としての開校となり、171名の入学生を迎えました。
戦後の学制改革を経て、昭和22年に男女共学の新制中学校を、翌23年には帝塚山高等学校を設置。昭和25年には森礒吉先生が学園長に就任し、のちに第2代理事長として学園を牽引しました。森先生は「幼児から青年までの一貫教育」の必要性を掲げ、創立10周年を機に昭和27年、帝塚山幼稚園および帝塚山小学校を開設。初等・中等教育の体制が整い、その後の学園発展の礎が築かれました。
中等教育においては、帝塚山中学校・高等学校でコース別中高一貫教育を導入し、生徒一人ひとりの個性を尊重し、その力を最大限に伸ばす教育を展開してきました。さらに平成19年には男子英数コースに「スーパー理系選抜クラス」を、平成25年には女子英数コースに「スーパー選抜クラス」を新設。これにより高等学校の大学進学実績は大きく飛躍し、現在に至るまで確かな成果をあげています。
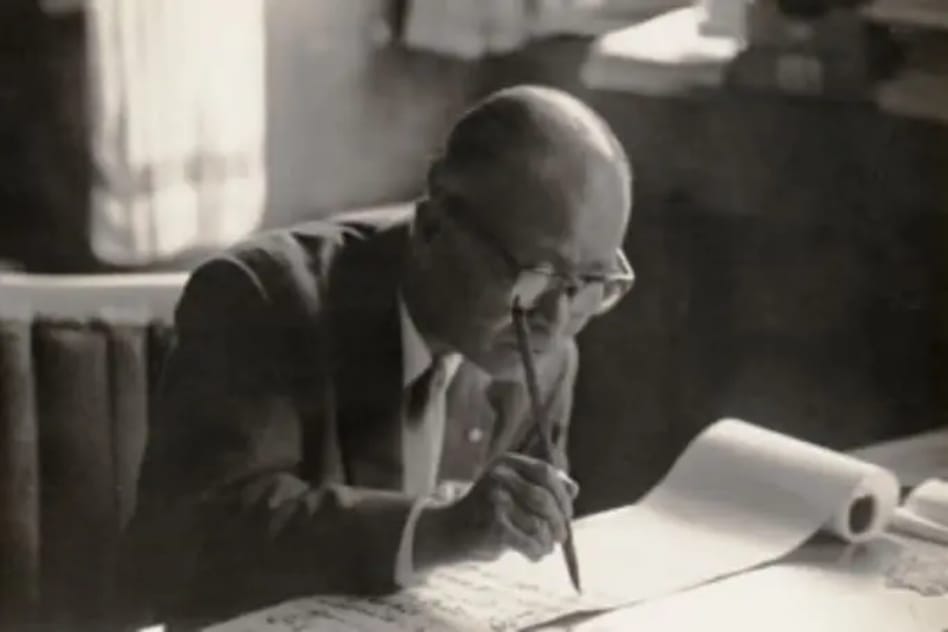

帝塚山学院の二代目山本藤助理事長の斡旋で、鉄鋼報国会から五十万円の寄付をうけて設立資金の基礎を固めた。学園が買収した土地と大阪電気軌道(現在の近畿日本鉄道)の金森乾次専務の多大な協力によって、「菖蒲池駅」と「富雄駅」との中間の土地十六万八千坪を学園設立予定地とする、新設した駅を「学園前駅」と命名された。(生駒郡伏見村菅原)
昭和16年(1941)財団法人帝塚山学園設立および帝塚山中学校設置を文部省に出願する。同年二月に認可されて、あやめ池遊園地内の航空科学館を仮校舎として、開学式ならびに入学式を同年4月10日挙行して、一学年生174名が入学する。
開校まもなく戦争がますます峻烈になって、食糧事情も悪化しているおりから学園が所有する二町歩余りの田畑を耕し、牛を飼い、稲を作り、玉葱を植え、芋をつくり、炭を焼くなど自給自足の一助のもと教員も生徒とともに励んだ。
学制改革が実施されて、昭和22年には新制中学校となる。翌、昭和23年には新制高等学校が併設されて、中学校には始めての女子生徒8名が入学した。
「父母と先生の会」や「体育後援会」を結成して、学園の再建にとりかかった。森礒吉校長が学園長を兼任され、なお大阪の帝塚山学院の学監をも兼ねられて、学園・学院のために日に夜についで奔命され復興するに至った。
時あたかも学園創立十周年に当たる昭和26年(1951)を記念して開設の計画を立て、翌、27年4月開校する。幼稚園は一年保育41名、二年保育65名であり、小学校は一年生22名で、幼稚園・小学校とも男女共学で始める。幼稚園長・小学校長は森礒吉学園長が兼任した。





沿革
| 昭和16年 | 帝塚山学院創立25周年記念事業として男子7年制高等学校設立を計画 帝塚山学園設立 帝塚山中学校開校(男子5年制) |
| 昭和22年 | 学制改革により新制中学校を設置(共学) |
| 昭和23年 | 新制高等学校を設置(共学) |
| 昭和26年 | 帝塚山幼稚園開園 帝塚山小学校開校 |
| 昭和31年 | 創立15周年記念式典挙行 |
| 昭和36年 | 帝塚山短期大学開学 創立20周年記念式典挙行 |
| 昭和39年 | 帝塚山大学開学 |
| 昭和40年 | 創立25周年記念式典挙行 |
| 昭和46年 | 創立30周年記念式典挙行 |
| 昭和56年 | 創立40周年記念式典挙行 |
| 昭和58年 | 高等学校に英数コース設置 |
| 平成3年 | 創立50周年記念式典挙行 |
| 平成5年 | ACJCと姉妹校提携 |
| 平成8年 | 中学校に英数コース設置(コース別中高一貫教育開始) |
| 平成13年 | 創立60周年記念式典挙行 |
| 平成19年 | 男子のコース改編 男子英数コース スーパー理系選抜クラスの設置 |
| 平成20年 | 男子英数、女子英数、女子特進、女子文理の4コース設置 |
| 平成22年 | 女子特進II、Iコース設置 |
| 平成23年 | 創立70周年 |
| 平成25年 | 女子のコース改編 女子英数コース スーパー選抜クラスの設置 |
| 令和3年 | 創立80周年 |